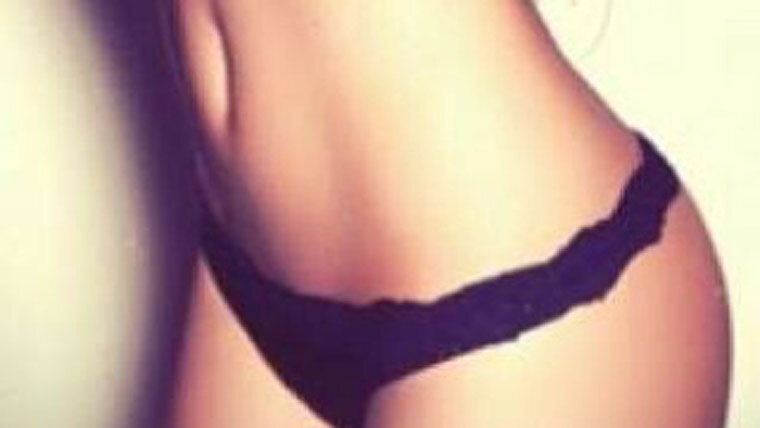もうどこへも行かないで・・・
それから2日ほど彼の姿を見ることはなく、心配になって海女さん仲間に彼のことを聞いてみることに。
すると、海女さんたちは、
「自宅を出て海女の仲間の家に行って、一緒に暮らしているみたいだよ」
どうやら仲の良い海女さん宅に、しばらく身を隠させてもらっているようだ。
それを聞き、すぐにケンタ君に会いに行った。
「今夜一緒に夕食を食べようよ。献立はケンタ君に任せるから」
そう言って、彼に食材を渡した。
その日の夜、ケンタ君は食材を持ってやって来た。
料理が得意とあって手料理を彼が作ってくれるので、バーでのバイト経験があった私は、カクテルを作ってあげることにしたのです。
作る際にはアルコールに弱いという彼のこと考えて、オレンジジュースを多めにしたスクリュードライバーを作ってあげました。
「あっ、美味しい!これだったら飲めるよ」
そう言って、一気に飲み干してくれました。
彼の手料理をいただきながらお酒も進み、お酒で緊張も解けてきたのか、彼は饒舌になってきたようです。
私は頃合いを見て、彼に抱きついて唇を重ねてみました。
先日のこともあるので、慎重に彼の体を愛撫してみた。
首筋、うなじ、肩、鎖骨、胸、背中、お腹、お尻、太ももなど、入念に全身の愛撫を繰り返して緊張をほぐしてあげます。
「私に全てを任せて、心配せずに一緒になろうよ」
そう言ってあげると、
「うれしい。もっと早く、美由紀さんに出会っていれば良かった」
彼は涙声で私に抱きついてきたのです。
彼を優しくベッドに誘導して寝かせると、薄暗い部屋の明かりの中で、彼のTシャツとジーンズを脱がし、ボクサーパンツ一枚の状態にしました。
そして、そっと優しくボクサーパンツを脱がせると、すでに彼の分身はいきり勃って、ブルンと勢いよく反り上がって飛び出してきたのです。
さっきまで緊張気味だった彼は、興奮で一気にスイッチが入ったのでしょう。
私のパンティーに両手を掛けて脱がし、薄い毛の先にある私の陰裂を見ると、脚を開けて陰部に顔を近づけてきた。
そこにあったピンク色の肉の突起を口に含み、舌先で転がしたり、口で吸ってみたりしてくる。
「あん・・・、あっ」
私はたまらず喘ぎ声を漏らしてしまった。
さらに、彼は蜜壺の周辺を舐め回してきたので、私は自ら脚を開いて、その脚で彼の上体を締めつけてみたのです。
「もう来てくれても大丈夫だよ」
そう言うと彼は、いきり勃ったイチモツを私の膣口に当てがってきました。
「こんな気持ちになったの初めて、もう好きなようにして・・・」
私は今までに経験したことがないくらいにすごく喘いだ。
彼は早る気持ちを抑えて、自分の分身で膣の入り口を十分に愛撫してから、ゆっくりと私の中に入ってきたのです。
すでに濡れすぼった私の蜜壺は、ケンタ君の屹立を抵抗なく受け入れました。
最初は浅く、優しく抜き差しを繰り返したが、だんだん辛抱できなくなり、深く、強くを繰り返し始める。
「私を離さないで、もうどこへも行かないで・・・」
私は泣きながら両手をケンタ君の背中に回して、強くしがみつきました。
と同時に、ケンタ君は限界に達してしまい、ありったけの精液を私の中にドバっと撃ち出したのです。
その夜以来、私たちは急激に親しくなり、私は毎日のようにやって来るケンタ君の食事や身の回りの世話をしてあげて、毎晩交わる日々を送りました。
最初はどちらかと言えば受け身一方だった彼も、日に日に積極的になっていきました。
海がしけて海女漁ができなくなった時などは、彼は明るいうちからやって来るので、
その日は2回も求めてくるようになりました。
ある時などは、疲れてケンタ君が私の好きなようにしてくれとベッドに大の字になると、私を裸にしてシックスナインの形になったので、フェラチオをしてあげたら、
「先輩の海女さんの猥談を聞いて、一度試したかったんだ」
と彼はちょっぴり恥ずかしそうに言った。
慣れてない、ぎこちない仕草がかえって新鮮で、かわいくて仕方ない。
ただ、このままでは大学に提出しなければならないレポートの作成に支障が出るので、昼間は机に向かい、夜に彼と過ごす生活にしました。
波風が弱い時には、ケンタ君は私を海に誘い出した。
中学高校と水泳部で泳ぎが得意だった私に、彼は潜り方や貝の探し方、取り方などを教えてくれた。
誰もいない月明かりの下で、お互いに激しく求めあったこともあった。
ずっとこのままでいられたら、どんなに幸せだろうか・・・。
しかし、そう思っている私の心を揺るがす出来事が起こるのです。